【徳永京子さんによる『Hello〜ハロルド・ピンター作品6選〜』的早孝起インタビュー&稽古場レポート】

『Hello〜ハロルド・ピンター作品6選〜』公演情報はこちら
『Hello 〜ハロルド・ピンター作品6選〜』の稽古場取材のため、11月23日(火・祝)、アトリエを訪ねた。
『Hello』は、副題にあるように20世紀を代表する劇作家のひとりで、ノーベル文学賞も受賞したピンターの短編6作を一気に上演しようという企画。文学座アトリエの会は、実験的な公演が行われる場所として長い歴史を持つが、その中でもかなり意欲的な部類に入るのではないか。
企画者は、この作品が初のひとり立ちの演出となる的早孝起。的早の指名に応えたのは、中村彰男、藤川三郎、石橋徹郎、上川路啓志、萩原亮介、寺田路恵、山本郁子、小石川桃子。
上演される『家族の声』『ヴィクトリア駅』『丁度それだけ』『景気づけに一杯』『山の言葉』『灰から灰へ』は登場人物の数が2〜8名で、稽古の参加者は日によって異なるそうだが、訪ねたのは幸運にも、出演者全員が揃う日だった。充実した時間を垣間見ることが出来たのだが、そのレポートの前に、どうしても企画の趣旨について詳細を聞きたくて的早に時間をもらったので、インタビューから読んでもらえたらと思う。
《的早孝起インタビュー》※写真は稽古場での様子
── やはりまず、なぜピンターか、しかも短編を6本もつなげて上演するという大変な企画を立てた理由からお伺いしたいです。
的早 そうですよね(笑)。ピンターの作品はどれも、人物同士のコミュニケーションが上手く行かないというか、分断されている人達が登場します。その分断の背景には、惨劇のイメージが共通してあると思うんです。出てくる人物が過去にそういった体験をしているかどうかの直接的な話に限らず、世の中全体が持つ惨劇のイメージが作品の奥の方にある。それによって分断された人達が、ある状況に閉じ込められているような戯曲というのが、僕が考えるピンター作品です。そしてその状況が、今の自分自身の周囲との繋がり方と近いというか、そういった惨劇のイメージが重なりに重なった上に僕らは生きていて、どんどん分断が進んでいるんじゃないかとずっと感じています。企画を提出したのは2年前ですが、その時も今も、ピンター作品が時代と合っているのではないかという気持ちは変わりません。
ただ、惨劇のイメージを伝えるのではなく、その背景の上で生きている(劇中の)人物と自分達が、本番を通して、その空間に共に生きていると感じられたらいいなと思っているんです。作品は一見、人物同士の分断がかなり進んでいてシビアな内容が多いですけど、だからこそ、お客さんと人物と俳優さんと座組全体とが出会い、寄り添い合うことで希望を見つけたい。それがピンター作品をやろうと思った理由です。彼の作品にはそういった、どこかで人を信じているというか、深いところで作者自身が人間の尊厳を信じたいと思っていたと感じるし、そういう舞台に出来るんじゃないかなと思っています。
── 「世の中全体が持つ惨劇のイメージ」というのは、人間が昔から繰り返してきた戦争や迫害やテロ、殺人や差別などの負の歴史の積み重なりが、無意識下の認知になって人類に共有されている、ということですよね。的早さんは「分断」という言葉を使われましたが、日常のレベルで言うと、知らない人と関わるのは危険だ、だから挨拶もしない、という時代を私達は生きている。
的早 はい。道を歩いていて倒れている人がいたら、声をかけようかとも思うけど、もしかしたら急に殴りかかって来られるかもしれないと思って一瞬、止まってしまう、みたいな。実際は殴られた経験もないし、そんなことは見たこともないのに、自分の中の何かが声をかけることを止めてしまう──。なぜそうなってしまったか、理屈だけで全部を理解するのは難しいですけど、完全に理解しなくていいと言っているところが、どこかピンターさんの作品にはある。そしてすごいのは、瞬間瞬間のやり取りはわかりやすい部分もあるんです。
── ピンター作品は、事態の全容はわからないけれどもとにかく不穏な緊張感が張り詰めていて、その中に時々、場違いのようなユーモアが挟まれていると感じていました。今の的早さんのお話を伺っていて、そのアンバランス加減が活かされるのかと感じました。そのベースを、上演ではどう組み立てていかれるんでしょうか?
的早 今回の企画を立てるに当たっては、ピンターさんのインタビューを読んだり、戯曲の元になっている事件やモチーフを調べたりしたりしました。それらを参考にしつつ気を付けたのは、こちらが説明しようとしたりとか、特に怖い人物を凶悪に描こうとすると、結果として、すごくお芝居が狭くなる、豊かさが無くなってしまうことです。これは稽古をしながら発見していったんですけど、どの人がどう悪いか探っていくよりも、稽古場にいるみんなで、シチュエーション、せりふのひとつひとつを「この人はなんでここでこんなことを言っているんだろう?」と考えていく。どの人物も「こういう人だから」と決め込まないで、常にひとりひとり対等な人間として発見し続けることを大事にしながら作品を築いています。
そういう意味で、小道具やセットも極力削ぎ落とす方向で進めています。何か(具体的な)物があると、この人はこういう人物と決まってしまうところがあるので。話ごとの転換も出演者がやる形です。
── 6作ありますから、出る本数に多少の差はあっても、俳優の皆さんは大変ですね。
的早 しかも、役だけでなく、役じゃないベースの人物も演じてもらいます。戯曲には、ただのリアリズムじゃないという部分と、ものすごくリアルに突き詰めて書いてある部分があるんですけど、全体のイメージが成立するように、ある人物達が意志を持って、ピンターの書いた人物達を舞台上に存在させるんだというつもりで出て来る。
── つまり俳優さんにとっては役が2つあるということですか? 『Hello』全体を通して存在する役があり、それがさらに個別の作品の役を演じる?
的早 そうですね。ネタバレになってしまいますけど、全体を通して存在するのは亡霊です。死者の目線で、歴史に消えていったり、今も消えていっている、閉じ込められた空間の抑圧された人達を演じるというか。
── ある種の劇中劇ですね。ということは、最初に仰っていた、積み重なった惨劇の歴史の層を、亡霊に行き来させるようなイメージでしょうか?
的早 狙いとしてはそうです。
── 戯曲の持つ不穏さ、残虐性が、それによってある距離や長い時間軸を持ちそうです。ただ、それだけでは、最初におっしゃっていたラストの希望には繋がらないですよね。「怖い人物を凶悪に描こうと」せず、優しく描くとかえって怖さが増すこともあるわけで、最終的な目的の「希望を見出す」は苦労のしどころなのでは。
的早 企画を出した時点で考えたのもやっぱりそこで、1本1本では希望にはならないところを、6本つなげることでどうにか、トータルで観てもらって最後の最後でもいいから、たどり着けないかと。企画会議でも、ごり押しで言い続けたって感じなんですけど(笑)。でも結局、「これが希望です」って僕が理屈で出したものだったり、僕だけが感じている「こういう形だったら希望だよね」を提示するのとは、稽古してみると違うレベルの話になっています。「こういうことだと思う」とやってみても思うように行かなかったり、「あっ、希望かも」と思ってもう1回見ると違って、また打ちひしがれてみたいな、希望と絶望を行ったり来たりの稽古をしています。
── だからこそ、上演の意味があると思います。翻って、的早さんがピンターを選ばれたのは、今の世界に進行している断絶に対して「これじゃいけない」という気持ちが強くあったということですよね。
的早 そうですね、シンプルに言ってしまえば、自分自身が苦しいですし。さらに周りを見れば、僕だけのことじゃない。選んだ戯曲は1980年〜1996年あたりに書かれたものなんですけど、そこですでにあったものが、年月を追うごとに顕在化している、日常化していると思って、これは今やっておかなければという意識はありました。

── この6作を選んだ理由は?
的早 最初に言った特徴はピンター作品のどれにもあるんですけど、分断されている状況自体が、他のピンター作品に比べてはっきりしているんです。やっぱり、いろいろなお客さんがいらっしゃるので、ある程度のわかりやすさを取っ掛かりにしたいというのはあって。それとバックにある惨劇のイメージが、相互関係や近いものがあると感じる引っかかりが強いんですね。それらが並んで影響し合うことで、1本だけだとどうとでもやれてしまったり、または、決め付けることになりがちなところから自由になって、かつ、最後に、この6本だからこそ、それぞれの人物ひとりひとりがいたんだということが繋がってくるのではないかと。
これは偶然なんですけど、順番を決めていった時に「よし、この並びがいいぞ」と自分で納得したのが、ちょうど書かれた年代順になったんです。それはきっと、ピンターさんの生きた時間──ある時に感じて書いて、時代が進んでまた書いてということ──が、人間の普遍的な足跡と近いものがあるんだと感じました。直接的な時代の流れを描く劇作家ではないですけど、時代の足跡と彼の足跡が、まさに重なって繋がっているんだと思いました。
── 上演順を決めるのは苦労されたのではと予想していたんですが、必然的であるように決まっていったんですね。
的早 テーマというかシチュエーション的にも、家族の話があり、仕事の話があり、仕事の話も人物の立場が違っていたりと、言ってしまえば人間のコミュニケーションを、家族という原点のところから、社会性が強い関係へと、徐々に広げている流れがある。そこは意識しました。

── ただやはり、ピンター作品は謎が多い。出演者やスタッフの方達と、どの程度、解き明かして上演に取り組んでいるのかを教えてください。具体的な答えを見つけて、せりふには出てこなくてもそれを共有して演じるのか、それとも謎は謎のままとし、答えは個人に任せているのか。
的早 稽古では基本的に解き明かす方法を取っていますが、解き明かしたものを説明しようとすると、観る人にとっては、また別のところが謎になったりして、やっぱり複雑なんです。ある謎が解けて「だからこっちの人が悪くてこっちの人が良い」だけの話になってもだめですし。解き明かしたものを、じゃあどこまでわかるように表現するか、それをもう一度みんなで探す。
亡霊というよくわからない存在をベースにしているのは実はそこを考えていて、変な言い方をすれば、出来るだけ早く観ている人が「これは全部わからなくてもいいんだ」と思えた方がいいというか。その前提をぼやっとやってしまうと、たとえばリアルに突き詰めようとしているところは、お客さんに「わかってください」と熱量を押し付けるだけになってしまう。そうならないよう、理屈でわからなくてもいいということをまず伝えたい。とは言え、理解したい人は理解してもらっていいという方針なんですけど。
── わかることが観ることのすべて、わからないとチケット代を損した気持ちになるという考え方は残念ながら広がっていますね。以前はもう少しわからなさに寛容だったと思うので、まさにそこにも分断があると個人的には感じています。そこと繋がる問題ですが、『Hello』というタイトルは、断絶してしまった人達への呼びかけから付けられたタイトルですか?
的早 6本全体のタイトルをずっと考えていて悩んでいる時に、ほんとにこれ、オカルトみたいな話なんですけど、夜、突然、「Hello」って声が聞こえた気がしたんです。「誰の声だ?」と考えたら、ピンターの声だと感じて。まだ具体的に演出プランを決める段階ではなかったんですけど、その時、全部の作品が終わって暗転した後に、スピーカーも何も無いところからジジッてノイズの音が聞こえて、それがピンターらしき声で「Hello…」と言って終わるというイメージが湧いて。実際にそうするかどうかより、そういう質感のものを自分はやりたいんだって思ったんです。
じゃあ、「Hello」って何だろうって思うと、今おっしゃったように出会うという意味はもちろんあります。断裂の状態でも出会うことが、まだ見つけていなかった希望への第一歩になるなと。その後、「He」で「彼」、つまりピンターであったり、「Hell」で切ると「地獄」だったり、最後の「lo」を少しずらすと「Help」になる。後付けですけど、どれも質感として作品にはまるので、これで行こうと決めました。
── 最後に出演者をどう選んだか教えてください。的早さんが希望したキャストの方に企画のプレゼンをして出演に至ったと思いますが。
的早 まず予定が空いているのかの確認をして、その後、おひとりおひとりに電話をし、出演オファーをしてOKをいただいた形です。6本を決めて企画で出した時点では、8〜10数人の幅で考えていたんですが、コンセプトを考え直したりするうち、8人で行けると。そこから、6本全体を通して舞台上にいてほしい方々を頭に浮かべながら、どちらかと言うと「この人にこの役」より、この人達が一緒にいたらこの作品の質感と相互にいい影響があるという──これもどこかイメージから入ったところはあるんですけど──考えました。世代が偏りたくないというのはまずありましたが、女性がやっても出来る男性の役もあると僕は思うので、そこは意識せず、8人の組み合わせの化学反応が作品と合ってくるであろう人を、オファーさせていただきました。
── お稽古されて、その狙いはいかがですか?
的早 すごく個性はバラバラなんですけども、やはり劇団だからなのか、何かが根底には共有されているのがすごく感じられて、それがすごくおもしろいです。そこは作品にとっても、皆さん同士にとっても、かなりいいことになっていると思っています。

── 的早さんのコンセプトも共有しやすかったですか?
的早 そこはバラバラですね。大きい部分──「Hello」って声が、ピンターの声が聞こえてとか、最後を希望にしたいとか、そういうことにはすごく皆さん乗ってくれて。「本当に出来るかね」と言いながらも一緒にやろうと言ってくれています。その先の細かい部分、作品ごとの進め方などは「こっちの方がいい」と言う方もいれば「それはちょっと違うんじゃないかな」と言う方もいらっしゃって、いい意味で、目標は共有しているけど、そこに向かう考え方は簡単には揃わない。でもそういう人間が一緒にいる状態は、ピンターの作品のあり様と近いところがあって、何だかおもしろいです。
《稽古場レポート》
すべて短編と言えど作品によって長短の幅があり、インタビューで的早は「背景に共通するものがある」と話していたが、事前に台本を読んだ私の感想は「シチュエーションも雰囲気もバラバラ」というもの。と同時に「短編だから、状況や登場人物のプロフィール、関係性といった説明が少なく、その分、余白が大きい」という共通項があり、その余白がどう扱われるのかに興味があった。

この日は、まず『丁度それだけ』の最後のシーン、そこから次の『景気づけに一杯』への転換と、『景気づけに〜』の一部をおさらいして、全員が出演する2本のうちの1本、オープニングの『家族の声』という順番で進んだ。最初に驚いたのは『丁度それだけ』の石橋のささやくような発声で、アトリエ公演とは言え、こんなに絞った声を使うのかと虚を突かれた。6本の中で最も短い同作は、ふたりの人物の短い会話の最後に、わかると恐ろしいオチが待っているという、切れ味の鋭いショートショートのような内容で、その軽やかさをスピードや笑いではなく、声の質感で表現したのが新鮮だった。
置かれていた黒いシンプルな背もたれ付きの椅子が、2脚から3脚に増えると、今度は『景気づけに〜』。本番で照明等がどうなるかわからないが、稽古ではシームレスな転換だった。これは登場人物が4人だが、この日は、主に会話を進めるニコラス(石橋)とヴィクター(萩原)のあるシーン。一方的に喋り続けるニコラスに対してヴィクターが笑ったところで、的早から「笑うのはいいんですけど、声が出るところまでは行かないでください。そこまで行くと(ニコラスに対する)警戒が解けるように見えるので」と演出が入る。それに石橋が「でもヴィクターが笑ったら笑ったで"こっちは冗談を言っているんじゃないんだぜ"というトーンで切り返せるけど」と意見を出し、的早が「だとしても、やはりもう少し抑えたほうがいい。ふたりが同調している空気にはならないようにしたい」と返す。実は私は、台本からはそこでヴィクターが笑うとは全く予想していなかったので驚かされたのだが、このやり取りを聞いて、すでにこのチームでは、一般的なリアクションの先の柔軟性が共有されているのを知った。

そこから、椅子に座っているヴィクターに対し、ニコラスが立ち姿勢で上から話すのと、しゃがんで下から話すのはどちらがこのシーンに適しているかの話へ。そのあとまた石橋が、あるせりふに「ここに"自分自身の"と入れたほうが良くない?」と提案、的早も「今のままでも百人のうち数人はわかるけど、それを入れたら伝わる人数が増えるでしょうね」と同意して、さらにこなれた日本語にするためにせりふの語順をその場で変更する作業が、ものの数分で完了した。翻訳劇ではよく「こなれた日本語」という言葉が褒め言葉として使われるが、こうした俳優の直感=小さな違和感への敏感なアンテナと、演出家の瞬時の決断でそれが生まれていくのだと知る。

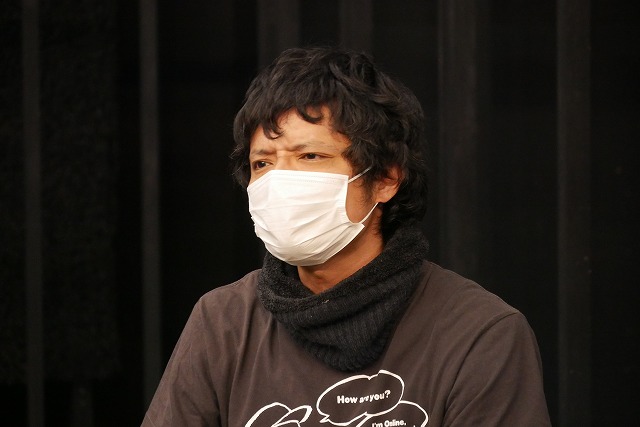
そして休憩を挟み、この日の、またおそらく、この作品全体の大きなポイントとなる稽古が始まった。最初のプログラム『家族の声』のオープニングだ。冒頭から8人全員が揃って登場し、順番にせりふを語っていくのだが、インタビューで的早が語っていたように、『家族の声』という物語を立ち上げるのと同時に、あるいはその前に、この場所に亡霊を出現させなければならない。つまり、ここにいる人達は『家族の声』の登場人物であり、それとは違う存在でもあるらしいと観客に感じさせたいという、企画のコンセプトを支えるシーンだ。


その前に『家族の声』について説明すると、戯曲が指定する登場人物は「声一:若い男、声二:女、声三:男」で、内容は手紙らしき文体のモノローグが並んでいるというもの。若い男は息子、女は母、男は父と、3人は親子らしいことはわかるが、彼らの話は微妙にずれていて、手紙は届いているのかどうかわからない。だから普通に考えれば3人の俳優が配役される物語で、これを全俳優でやると聞いて──驚いてばかりだが──頭の中にまず浮かんだのはクエスチョンマークだった。配役を書くと、声二を寺田と山本、声三を中村、声一を他の5人が演じる。私のクエスチョンマークが少しほどけたのは、最初の上川路から次の萩原へと、話者が切り替わった時だった。的早がそこで「分裂」という言葉を使った。それはすでに座組の間で共有されているらしく、声一、また声二を複数の俳優が演じるのは、その登場人物の分裂で、通常はあり得ない分裂が行われるのは、そもそも彼らが通常の存在ではないことを意味するということだ。
けれどもそれでオールオッケーには、当然ならない。先に書いた「俳優の直感=小さな違和感への敏感なアンテナ」がマックスで稼働しているからだ。この日、とりわけ違和感を表明していたのは、文学座の中でもベテランの山本だった。「実際には息子の声は聞こえていないのに、彼のほうを見ていてもいいの?」「見ながら"お前はどこにいるの?"と言うのはおかしくない?」と意見を言う。的早は「お互いを見ていないから分断というのはわかりやす過ぎる。見ているようで本当は見えていないことはある」「当事者同士だと、なぜこうなっているのかその時はわからなくても、第三者から見ると"こういうことを言いたいんだな"とわかる場合がある」と演出意図を説明。山本の疑問は皮膚感覚から来るものと感じられるが「想念では何でも出来るけど、実際に目の前にいて見ているのに届いていないという感覚でせりふを言うのは難しい」「見ているのに"お前はどこにいるの?"という関係を、初めて観たお客さんはわかるの?」と、亡霊という設定がつくり手同士の間で便利に使われることに警鐘を鳴らす、重要かつ知的な指摘だ。

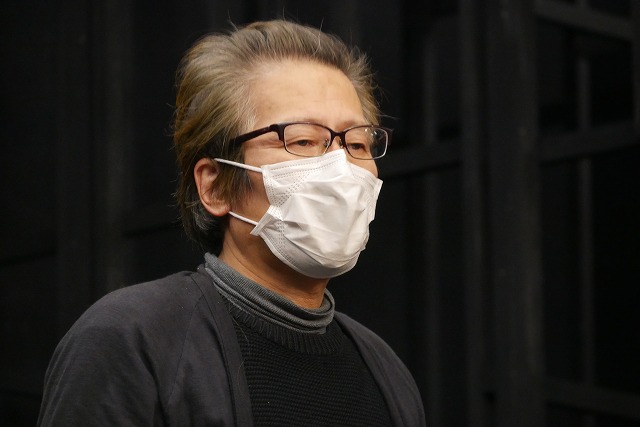
稽古は、同じシーンを繰り返し、少し進み、また止まる。その途中で石橋が「声二の手紙は、実際に(声一に)届いているんじゃないか。(自分達はこの戯曲を)何もかもわからない気になってやっているけど、住所もわかっていて、訪ねて行っているんじゃないか」と発言し、硬直しかけていた空気が変わった。これはハッとする指摘で、確かに私も「ピンター作品は謎だらけで難解」という前提を何の疑いもなく持っていた。けれども石橋の意見ではっきりと通る道筋が戯曲にはある。山本と同じ声二を演じる寺田も「少なくともこっちの思いは(声一に)届いているのかもね。だから(声一は)逃げよう逃げようとなっていくのかも」と。的早も「石橋さんの意見を取り入れてやってみましょう。もしかしたら届いていないかもしれないけど、お母さんだったらきっとこう返して来るはずだという思いは、声一が肚に持っていていいと思う」と応じる。

このあとも、修正というよりそれぞれの意見の交換で稽古は進んだ。ピークは『家族の声』のラストで、ひとりずつ舞台から去るのだが、実際にはおそく数分のシーンに次々と疑問と意見が出る。誰が誰にどんな気持ちで視線を向けるか、そらすか。声一と二と三の関係を改めて問い直し、と同時に、分裂した亡霊として抱えた気持ちも処し方も自問する。「声三の息子への言葉は(複数いる声一の)どこにかけるか。声二の存在をどの程度意識するか、自分はお前より息子のことがわかっているという優越感でいいのか」と中村。どんな気持ちでせりふを言っているかと聞かれた萩原は「階段の足音というせりふは、将来に対する不安を表現していると思う。そして今の自分について、母親に当てつけの気持ちもある」。声一はひとりずつ消えていくのだが、石橋は「俺はハケる時、(まだ舞台に残っている)上川路にちょっと視線を残そうと思っている。自分はいなくなるからもう関係ないじゃなくて、自分の分身に対して思いはあるはずだから」と。
ディスカッションは続き、それは文学座だからなのか、ピンターがそうさせるのか、この座組の持ち味なのか私には判断できないが、はっきり言えるのは、私が今まで見学した少なくない稽古の中で最も積極的に俳優が意見を言い、演出家が真っ直ぐそれに応じる現場だった。最後に的早が「すみません、明日までに整理の時間をください」と言った時、その場にいる全員が一瞬で柔らかな笑顔になったのも象徴的だった。最後に個人の見解を付け加えると『家族の声』のオープニング、声一の語り手が変わっていき3人目の藤川が話し出した時に「ああ、見えないバトンが渡されている」とはっきりと感じ、ここにいる人達はグループなんだと瞬時に腑に落ちた。中で共有されている「分裂」「亡霊」という概念とは異なるが、私なりに受け取るものがあり、モノクロだったピンターの世界に色がついた。きっと少なくない人が"私なり"の『Hello』を体験できるのではないかと思う。
(文・徳永京子)